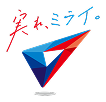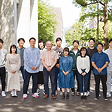ご挨拶
情報学部はチャレンジの場
情報学部は2025年(令和7)年4月、松山大学に誕生しました。デジタル人材の育成に関する社会のニーズを背景に地域の要望を受け、「情報Ⅰ」の科目が必履修として高等学校のカリキュラムに取り入れられた新しい学習指導要領で学んだ受験生が入学するタイミングで、松山大学のうち6番目の学部として開設されました。情報学部は地域における情報の専門分野の教育および研究の中核的拠点として新しくスタートしたばかりです。
松山大学には、「真実」、「実用」、「忠実」の3つの「実」からなる校訓「三実」と呼ばれる教育理念があります。「真実」とは、既存の「知」に満足することなく、真理を求めるために自ら学び、究め続けようとする態度です。「実用」とは、「知」を単に知識として学ぶだけでなく、自らの生活や仕事の中に活かすべく、常に現実的な問題を念頭に置きながら学ぶ態度です。「忠実」とは、人間関係や社会において、他者と誠実に向き合い、倫理的な態度はもとより、積極的に人と交わり、自らを謙虚に、そして互いの意見を尊重し共有しようとする態度です。100年を超える歴史と伝統のある松山大学では、校訓「三実」に基づく人材育成を続けてきました。
松山大学情報学部では、情報・デジタルの専門的知識・技術だけでなく,それを人と社会のために活用する際に必要な,論理的思考力,課題発見・解決力,共感力,コミュニケーション能力といった他者と協働できる力等の汎用的技能及び現代社会に必要な教養を身に付け,情報システムやメディアデザインに関する技術から新しい価値を創造し,デジタル技術の導入や運用を推進していく人材を養成すると教育目標を定めています。大学という学びの場は、ただ知識やスキルを身に付けるだけの時間と空間に過ぎないのではなく、仲間とともに切磋琢磨しながら交流し、人脈を広げるとともに、青春時代に人格を形成する貴重な場所という大きな意義があります。AIが進歩した先に、新しい価値を創造するという人間の存在意義が改めて問われ,次から次へと新しいテクノロジーが登場し続けたとしても,チームで社会的課題を解決することには普遍的な価値があると信じています。
情報学部のカリキュラムは、リベラルアーツ科目群、一般教育科目群、専門科目群、社会実践科目群および周辺科目群に教養を高め専門性を深めるための数多くの授業科目を配置しています。1年次の「情報学部基礎セミナー」では少人数の学生クラスに分かれて,情報学部教員の高度な専門性に触れることができます。英語や教養を身に付けるリベラルアーツ科目群をはじめ、一般教育科目群で幅広く学ぶほか、情報学概論やプログラミングといった必修科目で基礎を固めます。2年次に進級すると、情報システム分野とメディアデザイン分野の専門科目を学びます。さらに、共通領域としてデータサイエンスや機械学習(AI)に関する授業によって専門性を深めていきます。さらに、3年次には情報学部教員が開講する専門セミナーに所属し、それぞれ専門分野の研究を進めていきます。目標別プログラムではマイスター科目にまで到達し、その分野の専門家としての知識とスキルを身に付けます。このような学びを経て、最終年次には4年間にわたる学修の成果をまとめ、学士(情報学)の学位を得ることができます。
一方、アントレプレナーシップ入門やアートとデザインといった導入科目から出発し、社会実践科目群でキャリア探索やプロジェクトデザインなどの実践的な科目を配置していることも情報学部の特徴です。企業・団体等と連携し、社会的な課題をデジタル技術で解決するプロジェクトにも参加できます。このような実践的な学びの中で、コミュニケーション能力を高め、社会に直結した実務能力が培われます。
松山大学情報学部では、データベースや電子ジャーナル等が自由に利用できる図書館や最新の機器・設備とともに情報ネットワーク環境を整備し、キャリアマインドの育成、部活動・サークル活動、海外留学プログラムや社会連携プロジェクトなども用意して、学生の皆さんにとってチャレンジできる最適な実践の場を構えています。皆さんには、そのような成長できる挑戦の環境を存分に活用していただき、将来、デジタル社会の発展に貢献できる人材となることが期待されています。興味・関心のあることに挑戦を続け、夢中になって学ぶ中で気が付いたら力が付いています。このように学びに没頭できる環境は情報学部ならではの醍醐味だと思います。情報学部では、学生同士の交流とともに、学生のアイデアと教員の専門性の掛け合わせによって新しい価値を創造していきます。みなさんの目標を達成しようとする努力と挑戦に対して本学の教職員は全力でサポートします。
大きなことにチャレンジして、いっしょに情報学部をつくっていきましょう!
情報学部長 檀 裕也
概要
身に付けられる3つの力

01 論理的思考力・創造的思考力
客観的な事実(エビデンス)から論理的な推論を経て結論に至る思考過程を身に付けます。人工知能(AI)の進歩を背景に、ただ自明な結論を導くだけでなく、創造的な思考によって新しい価値を創造することが求められています。
02 課題発見・解決力
社会における課題に気づき,その課題の構造や背景を分析したうえで,最適なデジタル技術を選択し、解決する知識やスキルを身に付けます。人と社会のためにデジタル技術を活用することが求められています。
03 コミュニケーション能力
多様な人材で構成される社会で新しい価値を共創するために聴きかたや伝えかたといったコミュニケーション能力を身に付けます。チームで仕事をするには情報だけでなく感情を共有するための共感力も求められています。